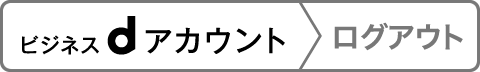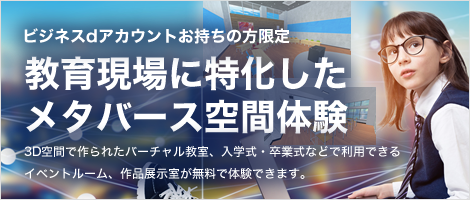『GIGAスクール構想緊急点検』 平井 聡一郎 氏
2022.10.31
GIGAスクール構想によって、各小中学校にICT機器環境が整備されて、約2年が経ちます。整備年度に差があるため、一斉のスタートとは行きませんでしたが、2022年度はおおむね整備後2年目を迎えたといってよいでしょう。2021年度は、「まず使う、とにかく使う」という年だったと思います。もちろん、私はその実態を否定しているわけではありません。むしろ当然、いや頑張っているレベルと考えています。各校40台しかPCがなく、先生方のICT活用のリテラシーもほとんどない状態から、よく、「まず使う、とにかく使う」レベルになったと思います。そこには学校を支える関係者の大変なご尽力があったことと推察します。特に教育委員会の担当者、学校管理職、各校のICTリーダーの皆さまのご努力には敬意を表します。
さて、そんなご努力でスタートを切ったGIGAスクール構想の2年目である2022年度の実態はどうなっているでしょうか?ごく一部とはいえ、各地の学校の授業を拝見しております私の目から見ると、ICT機器環境を活かした取り組みは、歩みを止めることなく確実に前進していると思います。多くの学校で、導入されたICT機器を児童生徒が、まさに文房具のように使いこなしている様子を見ることができます。さて、ここでGIGAスクール構想の本来の目的に立ち返ってみましょう。GIGAスクール構想は単なるICT機器環境の整備が目的ではなく、新学習指導要領の目指す学びを実現するための環境整備が主たる目的でした。では、その視点で2022年度のICT機器活用の現状を見直してみると、一見するとICT機器活用は進んでいるように見えますが、学びは従来型、つまり教師主導の一斉教授型の授業に留まっているように見えます。そこで、次年度に向けて実態を診断する点検が必要となってきます。
さて、私が「点検が必要である」と主張する理由の1つに、ネクスト・GIGAの機器整備の予算化があります。今回のGIGAスクール構想では国費を中心にICT機器整備が進められました。では数年後の機器更新はどうなるでしょうか?一般的に国の補助金というのは、キックオフのための予算措置であることが多いと思われます。国家レベルの新規事業を進めるためには、基礎自治体の足並みを揃える必要があります。そこで、キックオフスタートのために補助金を出して勢いをつけ、動き出したらその後は各自治体が独自に予算化して継続しなさいということです。しかし、コロナ禍の現状では、各自治体の財政状況は苦しいものがあり、ICT機器更新の独自予算化は困難な自治体もあるでしょう。この状況で財務省に予算請求するためには、GIGAスクール構想で整備されたICT機器が、今回の新学習指導要領による教育改革に大きく貢献しているという成果が必要になると考えます。ですから、学校、教育委員会はGIGAスクール構想の成果のアセスメントが求められるということになります。
では、ここで、どのようにアセスメントをするかを考えましょう。アセスメントとは「対象を数値により客観的な基準に基づき評価する」ことといえます。つまり、GIGAスクール構想が新学習指導要領の学びを実現に結びついたかを検証するためには、なにを指標に評価すればよいのか、なにを数値化すればよいかが重要となるわけです。そこで、わたしはその指標を全国学力学習状況調査の質問紙調査の設問から見出しました。その理由として、この調査が複数年に渡り継続的になされていること、全数調査により結果の数値の信憑性が高いこと、質問項目の質が高く、ICT機器活用のレベルを的確に評価できることの3点が挙げられます。質問紙調査は、文部科学省が学びの改革の実態をさまざまな視点で読み取ろうとしたもので、その中にICT機器に関する設問が組み込まれています。全国学力学の習状況調査の質問紙調査で注目すべき指標は次の5つの設問となります。これかの設問に対し、文部科学省の期待する回答は当然「毎日活用している」となります。
Q1 あなたの学校では,児童(生徒)一人ひとりに配備されたPC・タブレットなどのICT機器を、授業でどの程度活用しましたか。
Q2 児童(生徒)が自分で調べる場面(ウェブブラウザーによるインターネット検索など)でICT機器をどの程度使用させていますか。
Q3 児童(生徒)が自分の考えをまとめ、発表・表現する場面でICT機器をどの程度使用させていますか。
Q4 児童(生徒)同士がやりとりする場面でICT機器をどの程度使用させていますか。
Q5 あなたの学校では,児童(生徒)一人ひとりに配備されたPC・タブレットなどのデバイスを、どの程度家庭で利用できるようにしていますか。
ここで、これらの設問をSAMRモデルに当てはめてみましょう。すると、このように「代替」から「再定義」までの段階に当てはめることができると考えます。

※1 出所:Ruben R. Puentedura(2010)
私はICT機器活用による授業改革を英検の級によく例えます。それをSAMRモデルに当てはめると、「代替」は4級、「拡張」は3級、「変容」は2級、「再定義」は1級となります。英検も3級と2級の間には壁があります。3級までは、従来の学びの中でのICT機器の活用となります。2級となって初めて、新学習指導要領の目指す「主体的・対話的で深い学び」に近づきます。その「対話的」を具現化したのが「児童同士のやりとり」となるわけです。つまり、この質問紙調査の設問は、SAMRモデルの各段階をICT機器活用という視点で具現化したものであり、それを指標に各学校は自校の活用レベルを診断し、次の取り組みの目標を明確化して、ステップバイステップで学びの改革を目指していくことが可能となるでしょう。
GIGAスクール構想の実態を、質問紙調査の設問で緊急に点検することは、医療でいえば診察です。それによって現状を診断し、治療計画を立てていくことが今必要なのではないでしょうか?
執筆者紹介

平井 聡一郎(ひらい そういちろう)
文部科学省ICT活用教育アドバイザー
総務省地域情報化アドバイザー
経済産業省産業構造審議会教育イノベーション小委員会委員
略歴
公立小・中学校で教諭、教頭、校長として勤務。
教育委員会指導主事、教育委員会参事兼指導課長を経て、
現在、株式会社情報通信総合研究所特別研究員として勤務。
またドコモビジネス教育アドバイザーとして数多くの研修やセミナーを実施している。
主な研修内容
マインドセット/プログラミング/アプリ研修 など
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
ドコモビジネスコンタクトセンター
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)